【管理栄養士監修】骨粗しょう症予防・改善の食事
-
Q先日病院で骨粗しょう症予備軍だと診断されました。自分では自覚がなかったので正直びっくりしています。今からでも骨を強くする方法を教えてください。(42歳女性)
-
女性の場合閉経後にエストロゲンというホルモンの分泌が減少することも大きく関係しています。
エストロゲンは女性ホルモンの一種で、骨形成を促し骨吸収を抑制する働きがあるため、骨粗しょう症のリスクを低下させるものですが、閉経後はエストロゲンが減少するので骨密度が大幅に低下し、骨粗しょう症のリスクが高くなるのです。
骨の回復をはやめるために、まず意識してとりたいのがカルシウムです。
ここではカルシウムを効率よく吸収するために摂取するコツをお伝えしていきます。
骨粗しょう症予防の食事

骨粗鬆症は、骨の密度が低下して、徐々にもろくなり骨折しやすくなる病気です。
骨は、カルシウム・リン・マグネシウム・タンパク質が原料となっています。骨粗鬆症は骨の主成分であるカルシウム不足が問題です。
もし食事中に十分なカルシウムが摂取できない場合、体は骨に蓄積されているカルシウムを溶かして、血液カルシウム濃度を維持しようとします。
カルシウムが不足した状態が続いてしまうと骨や歯がもろくなるだけでなく、些細なことでもイライラしやすくなったり神経過敏などの症状が出てしまうこともあります。

カルシウムの多い食材の代表格としてしらす干し・ちりんじゃこ・桜海老・干し海老・切り干し大根・高野豆腐・あおさ・ごまなどがあります。
しらす干し100gには、カルシウムが約520mg含まれています。これは生しらすの約2.5倍ほどにもなります。
しらすにはカルシウムの吸収を助けるビタミンDも豊富に含まれているため、骨や歯を丈夫にする効果が期待できます。
しらす干しやちりめんじゃこはカルシウム量は多いのですが塩分が高めなので、塩分を控えたいときは湯通しして塩分を抜くことをおすすめします。
ビタミンDの多い食材ととる

ビタミンDを多く含む食材としては、魚類やキノコ類があげられます。
魚類・・・鮭・さんま・カレイ・ぶり・マイワシ・しらす干し・ いわし丸干しなど。
きのこ類・・・干ししいたけ・黒きくらげ・しめじなどは、食べる前に日光に当てることでビタミンDの量が増えます。
魚の中でも特にビタミンDが多いのは鮭です。
日本人にも馴染みのある鮭は、100gあたり32μgも含まれており成人の1日の必要量である2.5μgなので簡単に取り入れることができるため、キノコ類と鮭の組み合わせはおすすめです。
ビタミンKの多い食材をとる

ビタミンKの多い食材としては、納豆・海苔・わかめ・小松菜・ブロッコリー・モロヘイヤ・紫蘇などがあげられます。
ビタミンKは、骨にカルシウムが取り込まれるのを促しカルシウムが尿中に排泄されるのを抑える作用があります。
またビタミンKは骨に存在しているカルシウム結合タンパク質(オステオカルシン)を活性化させる働きがあります。
オステオカルシンは、骨の代謝や全身の健康に深く関わっているため若返りのホルモンとも呼ばれています。
マグネシウム
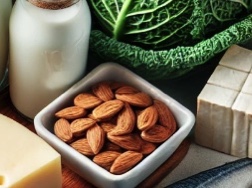
マグネシウムはカルシウムの代謝を助ける働きがあります。体内にあるマグネシウムの約3分の2は骨に存在しているので骨の重要な構成成分になっています。
マグネシウムを多く含む食材は、そば・豆腐・こんぶ・ひじき・金目鯛・するめ・ほうれん草・種子類(アーモンド、ごま・カシューナッツなど)があげられます。
カルシウムとマグネシウムのバランスは、カルシウムとマグネシウム2:1の比率がよいとされています。
カルシウムばかりに意識がいきがちですが、マグネシウムが慢性的に不足してしまうと狭心症や虚血性心疾患が起きやすくなるといわれています。
たんぱく質

骨の強さを保つために重要な要素。骨基質(骨を支える部分)の形成に関わります。
- 魚、肉・大豆製品、卵、乳製品
これらの食材をバランスよく取り入れて、定期的な日光浴や適度な運動も併せて行って、骨の健康がより一層強化されます。
カルシウムを阻害させる食材

カフェインを含むコーヒーやチョコレート、シュウ酸を多く含むほうれん草やナッツなどはカルシウムの吸収を悪くします。
またアルコールもカルシウムの吸収を阻害するため、適量(週3日以上の休肝日をつくる)を飲むようにしましょう。
また、リンを多く含むインスタント食品やスナック菓子などもカルシウムの吸収を悪くしてしまうので気をつけてください。
